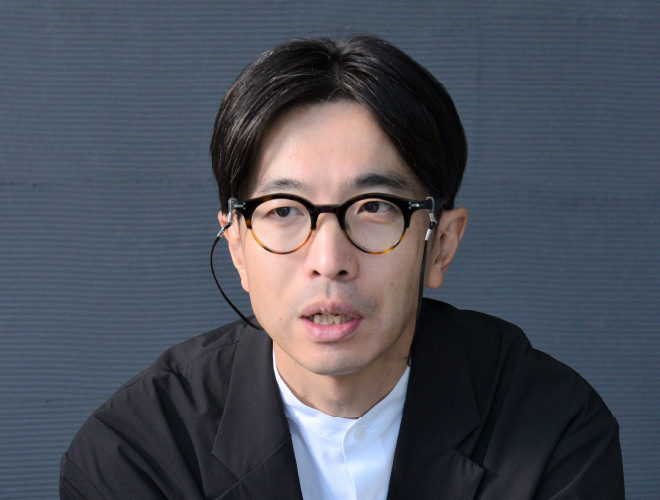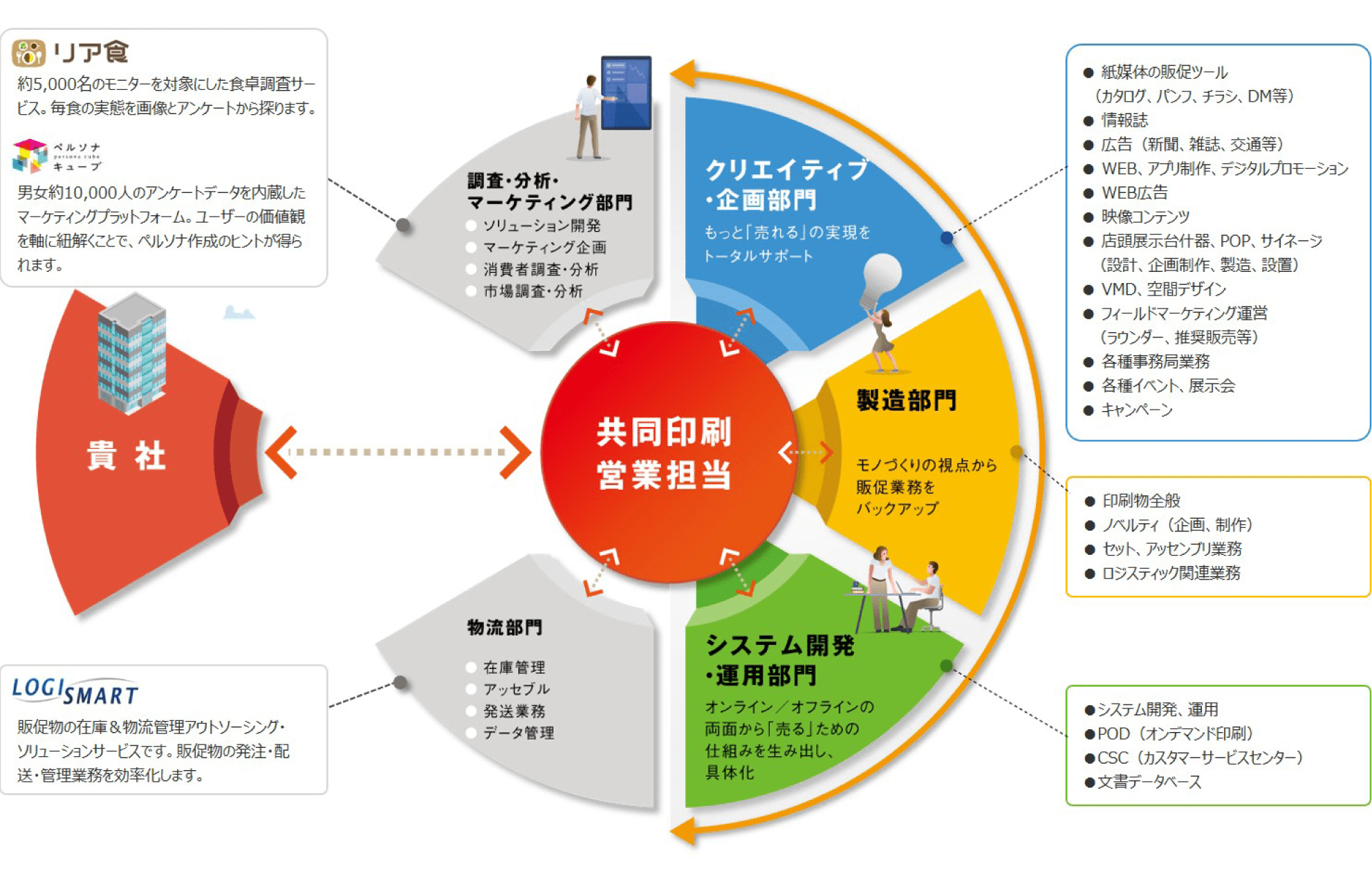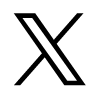NexTOMOWEL STORIES
-

CONCEPT
コンセプト編
TOMOWEL流、新しい「未来の支え方」
二人の役員が語る、「支える」ビジネスの本質と未来。そして、TOMOWELのさらなる進化とは?
-

STORY01
まなび編
「まなび」で、企業の未来を支える!
インナーコミュニケーションを支えるために。企業に役立つ「新しいまなび」を開発するプロジェクト。
-

STORY02
カードマジック編
法人向けキャッシュレスの未来を支える!
TOMOWEL共同印刷の社内ベンチャー第1号は、「立て替え精算」を解決するソリューションビジネス。
-

STORY03
ヘルスケア編
企業のヘルスケアで、未来を支える!
なぜ印刷事業を行うTOMOWEL共同印刷が、企業の「健康経営」を支えるビジネスを展開するのか?
-

STORY04
公共サービス編
BPO+BPRで、自治体の未来を支える!
社会課題の解決を、自治体の「効率化」で支える。鍵となるのは、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。
-

STORY05
環境包材編
パッケージ技術で、未来を支える!
持続可能性を支える、「守る機能」と「やさしい素材」。そして、循環型社会の実現に必要な姿勢とは?
-

STORY06
プロモーションメディア編
コミュニケーション設計の最適化で、
販売促進の未来を支える!デジタルも紙も。さまざまなメディアを融合することで、企業と消費者の「コミュニケーション」を支える。
-

STORY07
新素材開発編
新素材・新材料で、未来を支える!
印刷技術で、印刷物以外のものをつくる。この挑戦に必要なのは、意外な着眼点と「共に」の姿勢。